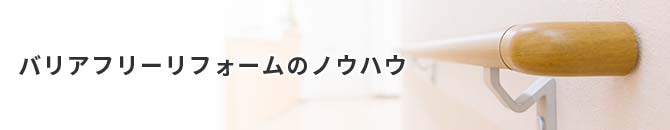
リフォームポイント
色覚バリアフリーリフォームの6つのポイント
公開日:2016年09月20日

色覚バリアフリーとは、色覚が正常ではない人にも認識できるような色やデザインを採用することです。
高齢になると物を見るときにピントを合わせる役割を持つ水晶体の機能が衰えるため、物がぼやけて見えます。そして眼の老化現象ともいえる白内障によって水晶体が白濁し、色を識別することや奥行きを正確に判断することが困難になっていきます。高齢者が白内障を発症する確率は、80歳以上でほぼ100%です。老化と白内障は切り離して考えることができません。
高齢者が段差に気付かずにつまずきやすくなる、あるいは何かにぶつかりやすくなるのはこのためです。
白内障では青や緑は見えにくく、ピンクやオレンジは同じ色に見えます。同系色では色の区別がつきにくいため、段差や凹凸のある場所は、はっきりと色の違いが分かる配色にするとよいでしょう。また、輝度の高い色や強い光に弱くなるので、照明は通常よりも少し明るめに設定する必要がありますが、明るすぎると逆効果です。
このようにバリアフリーのリフォームでは、識別しやすい色を採用するなどして、色覚バリアフリーを意識した配色も非常に重要です。手すりを設置したり、段差をなくしたりすることと同じように、住宅内の色あいや明るさの調整もバリアフリーでは大切です。インテリアや内装の色使いで注意したいポイントをいくつかご紹介します。
1.玄関の配色
玄関の三和土(たたき)と“上がりかまち”は通常大きな段差になっています。大きい段差は昇降しにくく、小さい段差はつまずきの要因になります。段差を完全になくしてしまう方法もありますが、色をはっきりと分ければ段差を見分けやすくなり、つまずき事故などを防止することができます。
2.階段の配色
階段の側面部分にあたる蹴り上げと、足を置く部分にあたるふみ面の色にはコントラストをつけて、視力が低下している人にも高さが分かりやすいようにすると良いでしょう。階段でのつまずきや踏み外しは、転落など重大な事故につながりやすいため、優先的に取り組むべき場所です。
3.床と壁の配色
高齢になると、水平な床と垂直の壁の境目も、似たような色を使うと判別しにくくなります。境目が分からずに足や頭をぶつけてしまう危険があるため、壁と床は似たような色にせず、コントラストをつけて見分けやすくしておきましょう。
4.家具の色
一体感を出して部屋を広々と見せるため、壁や床の色と家具の色調を似たようなものにする人がいますが、バリアフリーの観点からはお勧めできません。歳を取ると見分けづらく、足などをぶつけやすくなります。違う色を選ぶようにしましょう。
5.脱衣所の配色
脱衣所と浴室の洗い場の色には変化をつけたほうが良いでしょう。段差がある場合はつまずきの防止になり、段差がない場合は境目が分かりやすくなる効果があります。滑りやすい場所でもありますので、特に気をつけたいところです。
6.浴室の配色
浴室の洗い場と浴槽の色が同じというケースが多いですが、色の判別能力や遠近感が衰えている高齢者にとってはとても危険です。浴槽に手をつこうとして転倒するなど、重大な事故につながる可能性があるため充分な注意が必要です。