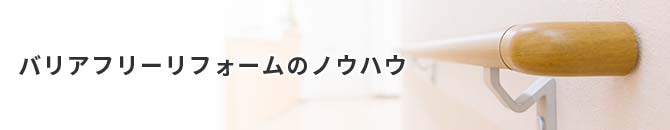
リフォームポイント
トイレのバリアフリー工事の種類
公開日:2019年05月10日

ひと昔前の住宅では、バリアフリーとは言えない住宅がほとんど。特にトイレは毎日使うとても大切な設備ですが、高齢化に伴い自分ひとりでは使いづらくなり、また、介護する立場になった際も非常に介護しにくいスペースです。
バリアフリーは住宅を計画するのに重要な要素です。トイレまわりをバリアフリーリフォームする際の工事には、どのような種類があるかを見ていきたいと思います。
トイレと廊下の段差解消
昔に建てられた家でよく見られるのが、トイレの段差です。廊下からトイレに入ろうとする際に、段差があることが多い家があり、バリアフリーを考える上で段差解消はまず最初に考える工事でしょう。
段差解消の方法
昔の戸建住宅で廊下とトイレの床段差がありますが、多くの場合廊下よりトイレの床が下がっているかと思います。これはトイレ室内を洗った際の水仕舞のためだと思います。床をそのまま水洗いできるようにしているため、トイレ床もタイル張りのトイレが多いのではないでしょうか。
段差解消をするには、便器を外して、給排水管配管をやり直し、床組みをして廊下とフラットにします。その後トイレの内装を張って、便器を取り付けます。トイレ床を上げて廊下の床と合わせます。
床の段差だけでなく、扉の枠の出っ張りも解消することを考えなければなりません。開き戸だった場合は引き戸などにして解消しましょう。
昔のマンションには廊下とトイレに段差がある理由
昔のマンションでは、廊下とトイレの床段差がある場合があります。この場合、戸建てとは違って必ず廊下よりトイレの床が上がっています。これは、トイレ排水管を排水竪管につなぐためです。
排水竪管はマンションの上下階を貫通している共用のものです。この排水竪管にトイレの排水管を床下で接続するために、床下にある程度の空間が必要になります。その空間をつくり出すために、床を上げているのです。ちなみに、新しいマンションでは、コンクリートスラブ側を下げて空間をつくり出しているので、廊下とトイレの床がフラットになっています。
このトイレ排水管と排水竪管のつなぎの位置を変更することはできないため、リフォーム工事をした場合でも、トイレ床を現状より下げることはできません。したがって、廊下とトイレの床をフラットにしたい場合は、廊下側を上げる事になります。
マンションで段差解消する際の注意事項
前述の通り、マンションの段差解消を解消するには「低い床を高くする」事が必要です。そうすると、お部屋の全体の床段差をなくすためには、廊下やリビング、洋室など全ての低い床を高くしなければなりません。そうすると、大がかりな工事となり、工事費も高額になります。また、部屋全体の床上げを行うので、天井との距離は近くなり、天井が低く感じられるようになるので中が必要です。
手摺の設置
トイレ内に手摺を設置する場合は、便器の左右横に設置する方法と、壁に設置する方法があります。便器の左右横に設置するのはアームレストタイプの手摺です。便器をまたぐように設置する置き型タイプとなります。また、壁に設置するのは壁にビスで固定する手摺です。手摺は非常に力がかかるので、壁下地を設け、手摺をしっかりビス固定する必要があります。手摺形状は一般的なI型の他、垂直+水平のL形のタイプもあります。
入口扉を引戸に交換
床段差解消や手摺設置と並んで、バリアフリーリフォームの王道のひとつは「引戸」です。トイレの空間は狭いので、多くの場合廊下側に開く外開き戸になっています。足腰が弱ると、開き戸の開閉は結構大変なものです。壁に引戸の引き代があれば、引戸にすることは可能です。上吊りタイプの引戸にすれば割と簡単に交換ができます。
また、2枚連動引戸にすれば同じ幅で開口部を大きくとることが可能となります。高齢者はもちろん、介護する側になって考えても、開口部を広くできることは非常に有効です。
車椅子が通れるように拡張
車椅子でトイレを使用し、かつ介護も考えると、トイレ室内面積は約1坪(180cm×180cm)必要です。つまり、通常のトイレの倍以上の面積が必要となります。トイレは日常の事ですので、車椅子使用の場合は拡張する事をお勧めします。リフォームの事例としては、洗面室とトイレを一体化して拡張する、というアイデアもあります。
拡張リフォームする際の注意点
戸建ての場合は、在来工法の柱や筋交い入りの壁、2×4の構造壁で水回りが囲まれていると柱や壁が撤去できず拡張が難しくなります。また、マンションの場合も同様に水回りがコンクリート壁、もしくは、ブロック壁で囲まれている場合は注意が必要です。構造的に撤去できる壁かどうかの事前検討が必要で、撤去できる場合でも解体時の騒音・振動が非常に大きく、近隣居住者にはかなりの迷惑をかけることになります。
拡張リフォームする場合は、構造をよく見極めて計画するようにしましょう。
照明に人感センサー設置
照明のスイッチのON-OFFも結構煩わしいものです。人感センサー付きのスイッチにするか、もしくは、ダウンライトに人感センサー付きのものを使用すれば、ON-OFFの手間が省けて非常に便利です。
トイレ内に暖房を設置する
バリアフリーのひとつとして、ヒートショックを防ぐということも重要です。トイレは基本的に暖房の取り付けは考慮されていないため、冬場はトイレが寒いと感じる方は多いのではないでしょうか。特に戸建てで窓がついている場合は、強烈な寒さを感じる場合もあるでしょう。
温暖差を少しでも和らげる方法として、トイレ内に暖房設備を設置するという方法です。
床暖房
冬のトイレ使用は寒いものです。冷え込むトイレなどで高齢者を襲う「ヒートショック」も社会問題となっています。そこで、トイレ室内を大幅にリフォームする際は床暖房を設置してはいかがでしょうか。
壁パネルヒーター
壁下地を施して、ビスで固定するパネルタイプのヒーターもあります。床暖房と比較すると設置は簡単です。
ヒーター内蔵照明器具
ヒーターを内蔵しているダウンライトもあります。天井からの暖気がここちよいです。もちろんヒーターのON―OFFができるので、夏はダウンライトのみで使えます。
トイレ本体のバリアフリー機能
最後に、トイレ本体を取り替えて、楽にトイレで用を済ますことができるようにすることも、バリアフリーでは必須です。トイレの便利機能をいくつかご紹介します。
一番簡単にできるので、まずは本体取り替えることから考えてみてはいかがでしょうか?
補高便座
便器の立ちすわりを楽にするために、座面を高くした便座です。商品によって違いますが、3cmあるいは5cm高くなるタイプのものがあります。また、便座が電動で昇降し、立ち座りをサポートする電動リフト機能付き便座もあります。
自動洗浄
便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流す機能です。いちいち振り向いて手を伸ばしてレバーを回す手間が省けます。
フタ自動開閉
フタ自動開閉機能付き便器は、便器に近づくとセンサーが感知してフタが自動的に開くので、知らなかったら結構驚きます。また、使用後は自動的にフタが閉まります。この機能により、開閉するためにかがまなくてもいいので、腰への負担を軽減できます。また、閉め忘れがないので、暖房便座の保温性が高まり、節電にも効果的です。
壁付けリモコン
昔の洗浄便座は便座の横にスイッチが並んだ袖リモコンがついていました。これは体をひねって苦しい体制でスイッチ操作をしなければならず、また、袖リモコンが邪魔でトイレ室内を洗いにくかったりしました。壁付けリモコンにすれば、無理のない体制で洗浄便座のスイッチ操作ができ、また、便器を洗浄する際もタンクのレバーを回す必要がなく、壁リモコンのスイッチで洗浄できますので、かなり楽になります。
まとめ
自分自身が高齢化する、もしくは高齢の親を介護する際には、トイレのバリアフリーリフォーム工事は必須です。ひと言でバリアフリー工事といってもその内容は様々です。使用する方の状況や予算などをいろいろ検討のうえ、納得のいくバリアフリーリフォームを行ってください。