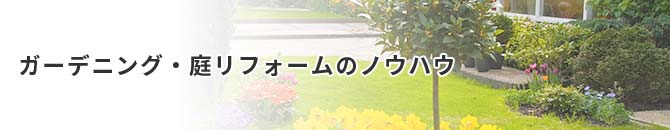
基礎知識
植栽の役割と植木の分類とその特徴をご紹介
公開日:2019年06月20日
植栽の役割

一口に植栽と言ってもその種類はさまざま。そして植栽がもつ役割もまたひとつではありません。ここでは、植栽の代表的な役割についてご紹介します。
プライバシーを守る
植栽には、プライバシーを守るという大きな役割があります。門まわりや庭に植えられる植栽は、道路やアプローチから住宅内部への視線をさりげなくブロックします。
外部からの目線を遮るには、基本的に常緑樹が適しています。落葉樹では、冬に葉を落としてしまうためです。また、大きく育つ樹木では、庭を狭く見せたり圧迫感を感じさせたりすることがあるので、低木や中木を選ぶとよいでしょう。
かつて、プライバシーの保護の目的で盛んにつくられた高いブロック塀は、閉鎖的であったり、あるいは、地震など災害発生時に倒壊の危険があったりと、今ではあまり好まれなくなっています。一方、生垣などの植栽は安全性が高く、自治体によっては推奨金の制度を設けているところも少なくありません。リフォームを機に自宅の緑を増やしたいという人は、最寄りの自治体に一度確認してみましょう。
日差しを調整する
植栽の大きな働きのひとつに、室内に入る日差しを調整してくれることが挙げられます。目的に合わせた木の種類や高さを選んで植栽することで、住宅への採光や遮光をある程度コントロールすることが可能です。
たとえば、植栽によって真夏の暑い時期には涼しい木陰をつくり、西側の樹木は強い西日を遮ることができます。逆に、冬に日差しが欲しい場所には、落葉樹を選んで植えることで暖かい陽の光を確保することができます。
四季を感じる
植栽には、季節感を演出するという役割があります。自然は人に、楽しみや癒しを提供します。特に都心部では自然を感じる空間がどんどん少なくなっている昨今、一般住宅の植栽は大切な自然です。
一年を通じて緑を落とさない常緑樹の美しさばかりではなく、色とりどりの花を咲かせる木は視覚や香りでその季節を感じ取ることができます。また、植栽で特に人気が高い果樹などの実をつける木は、四季折々の表情を見せてくれる他、食すという楽しみも与えてくれます。季節感のある植栽は、そこに住むものはもちろん、家の前を通りかかる人々にとっても楽しいものです。
植木の分類
植物には数えきれないほどの種類があります。すべてをご紹介することはできませんが、植栽として使われる植物にはどのようなものがあるか、分類ごとにそれぞれの特徴を説明します。
葉を落とす木と落とさない木
樹木には時期が来ると葉がなくなるもの、常に葉をつけているもの、気温などの環境に合わせて変化するものがあります。
常緑樹

常緑樹とは、年間を通して葉がついている木のことをいいます。葉の色は濃い緑色で、厚みがあり、硬いのが特徴です。常葉樹にも葉の入れ替わりはもちろんありますが、少しずつ行われるため目立ちません。中には新葉が出る時期に合わせて落葉し、短期間で新しい葉と入れ替わるタイプの木もあります。
庭の植栽として代表的な常緑樹は、高木・中木のアカマツ、キンモクセイ、クスノキ、サザンカ、低木・地被類のヤブコウジ、センリョウ、サツキツツジなどです。
落葉樹

落葉樹は春に新芽を芽吹き、新葉が数カ月で落葉します。葉が落ちた落葉樹は、次の春まで葉を一切付けません。一般的に夏には新緑や花を、秋には紅葉を、冬には落葉した枝ぶりを楽しむことができます。
1年を通して変化を楽しめる、観賞に適した植物といえるでしょう。常緑樹と比べるとソフトな印象の見た目も魅力です。また、夏は葉が日除けになり、冬は枝の間から陽ざしを取り入れることができるため、実用性も兼ねた使い方もできます。
高木・中木ではイチョウ、ケヤキ、ハナミズキなどが、低木・地被ではアジサイ、ヤマブキ、シモツケなどが庭の植栽としてよく使われます。
半常緑樹・半落葉樹

半常緑樹・半落葉樹とは、自生地では常緑樹だが、環境の変化によって冬期にある程度落葉したり、自生地では落葉樹だが環境によって一部の葉が落ちずに越冬したりする木のことです。庭の植栽として使われる代表的な樹種にアベリア、プリペット、シマトネリコなどがあります。
温暖な地域では常緑樹に分類されている樹種でも、寒冷地では落葉するといった場合にも半常緑樹と呼びます。特に東北より北の地域では、落葉することを認識した上で管理することが大切です。
陽の光を好む木と嫌う木
樹木には太陽の光が苦手なものもあれば、陽の光が無ければ育たないものもあります。そのため樹木の特徴によって、植栽に適した環境が異なります。
陽樹

陽樹とは、日当たりの良い場所に生息し、明るい環境を好む樹木です。生育するのに多くの日照を必要とします。一年を通して日当たりが良い南側の庭に適しています。
庭木にはオリーブ、キンモクセイ、ハナミズキ、アベリア、ヤマボウシなどが、草花にはスイセン、ワスレナグサ、カロライナジャスミン、ゼラニウム、アイリスなどがあります。
南側の庭に植栽する場合でも、高木、中木によって日影ができる場所に低木や草花を植栽すると、日照が足りず育たないので注意が必要です。
中陽樹

中陽樹は適度な日当たりと日影を好み、陽樹と陰樹、両方の性質を持ち合わせたような樹木です。午前中は日当たりが良いが午後は日影になる、東側の庭に適しています。西側にも植栽できますが、西日を嫌う植物も多いので注意しましょう。たとえば常緑樹のシラカシなどは、比較的西日に強いといわれていますのでおすすめです。
庭木にはアジサイ、イチジク、ビワ、ナツツバキなどが、草花にはインパチェンス、アルケミラモリス、クリスマスローズ、シュウメイギクなどがあります。
陰樹

陰樹とは、日当たりを嫌い、暗くて湿気のある場所を好む樹木です。日当たりの悪い北側の庭や、高木、中木によって影ができる場所へ植えるのに適しています。ただし風や寒気に弱いものもあるため、一年を通して日照が期待できない場所や寒冷地域などでは、陰樹の中でも耐寒性のある樹種を選ぶと良いでしょう。
庭木にはヒノキ、ヒイラギ、アオキ、アセビ、センリョウなどが、草花にはシダ類、タマリュウ、オダマキ、ヤブラン、ツワブキなどがあります。
樹木の高さの違い
植栽では高く成長する木、それほど高くならない木、背の高い木と低い木の中間、この3つに分けられています。成木時の高さで分類する場合もあれば、剪定などの手入れによって高さをコントロールして分類する場合もあります。たとえば背の高い樹木であっても、剪定によって常に低く保っていれば背の低い樹木として扱われる場合があります。
高木
高木とは、植栽時に3m以上ある樹木および成木時に5m以上成長する樹木のことを指します。植栽として使用される代表的な高木には、ケヤキやイチョウ、ソメイヨシノやマツなどがあります。
高木は植栽の中心的存在となるだけでなく、木陰を創出したり、広がりのある空間を演出したりすることができます。ただし、高木は将来を見据えた選定が重要となるので注意しましょう。特に成長途中の高木を植える場合には、成長後のイメージや必要なスペースの確保、定期的な剪定の計画をたてる必要があります。
中木
中木とは、植栽時に1.5~3m程度および成木時に2~5mに成長する樹木のことです。高木でも剪定による管理によって3m以下の高さに保たれている樹木も、その多くは中木として扱われます。植栽として使用される代表的な中木には、ツバキやサザンカ、キンモクセイやライラックなどがあります。
中木は、人の目線の高さに枝葉が生い茂るため、視線を遮る効果があります。目隠しとして用いるほか、並べて植栽することにより、エリア分けや垣根としての役割を持たせる使い方にも適しています。高木との高さの違いを利用し、奥行を演出することも可能です。ただし、見通しを確保する必要のある場所では、目線の邪魔にならないよう植栽の配置に注意しましょう。
高木ほどではありませんが、中木の中でも大きく成長する樹木があります。剪定などの手入れがどの程度必要になるのか、あらかじめ把握した上で植栽することが大切です。
低木
植栽時に1m未満で、成長しても1m前後の樹木のことを低木といいます。剪定によって1m前後に管理されている樹木も低木です。植栽として使用される代表的な低木には、アジサイやバラ、ツツジやジンチョウゲなどがあります。
低木は人の目線よりも低いため、圧迫感を与えることなくエリアを区切ることができます。また、群植することで、地表の乾燥を防止する効果も期待できます。
ま和風洋風を問わず、幅広く利用できるのも魅力です。同種の樹木で統一感を持たせる植栽はもちろん、違う種類の低木をおり混ぜることによって、四季折々の姿を楽しめるよう計画することもできます。
その他、樹木や植物の種類
植栽の中には、幹によって自立するものもあれば、そうでないものもあります。ここでは、自立しないタイプの植栽についてご紹介します。
地被類・下草類
地被類とは、地表を覆うようにして使用する植物のことです。樹木に限らず、芝やタマリュウといった雑草も含まれます。景石・灯籠等の添えとして植栽されたり、土の流出を防ぐ植えつぶしとして使われたり、あるいは、根じめや縁取りとして植えられたりします。
常緑樹にはアジュガ、エビネ、シダ類、シバザクラなどがあり、落葉樹にはアマドコロ、イカリソウ、スズラン、スイセンなどがあります。高さを出すことを目的としておらず、住宅のエクステリアのほか、屋上緑化などにも利用されています。
ツタ類・ツル類
建物や他の植物に伝わって伸びたり、地面を這ったりして成長していく植物のことをツタ類、あるいはツル類といいます。樹木と雑草が存在し、吸着、絡み、垂れ下がり、巻き付など、その成長のしかたにはさまざまな特徴があります。主に棚やフェンス、アーチなどに目隠しやデザイン性をもたせるために植栽されます。
常緑樹にアイビー類、イタビカズラ、カロライナジャスミン、クレマチスなどが、落葉樹にツルアジサイ、ナツヅタ、アケビ、キウイなどがあります。
植栽選びのポイント
植栽を選ぶ際には、日当たりや土壌など、庭に適した植物であるかどうかを考えるとともに、生き生きとした庭を演出するため、複数の植物をバランス良く配置することがポイントです。高さや色に変化をもたせれば、視線を楽しませることができます。
しかし、植物は見るだけのものではありません。見て、触って、香りを楽しむものです。トゲのある植物や、不快な臭いを発する植物には充分に注意が必要です。
充分な広さがあれば、植木を彫刻のように刈り込んだ仕立物中心の庭にするのも良いでしょう。格式高い印象になります。また近年では、必要最低限の剪定にとどめる、ほぼ自然のままの樹木も人気です。落葉樹を植えれば、四季の移り変わりを楽しむことができます。