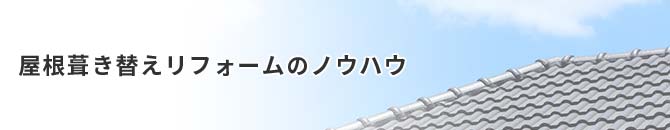
基礎知識
屋根葺き替え工事の工程とルーフィングの種類と特徴
公開日:2019年07月09日
屋根葺き替えの工程

葺き替えの工程は屋根材の種類によって異なります。ここでは「瓦」「スレート」「ガルバリウム鋼板」を例に挙げ、それぞれの工程をご紹介します。
※工程1から工程4までは共通です。
工程1:既存の屋根材を撤去
葺き替えですので、既存の屋根材を撤去する必要があります。葺き替えには、撤去・廃棄の費用が含まれているはずです。
見積もりの明細の項目にも明記されているか確認しましょう。細かく明記がない場合は、こちらから指摘して詳細な見積もり明細書をもらうことをおすすめします。
工程2:垂木の施工
屋根の葺き替え工事、最初の工程は垂木の施工です。垂木をすべて新しいものに交換するか、部分的に補修するかは劣化の程度によって変わります。
垂木とは、野地板を支えるための建材のことで、屋根を支える基礎部分です。屋根の一番高いところである棟木から、軒先である桁の間に取り付けられる細長い木材で、家でいうところの骨組みにあたる部分といえば、イメージしやすいでしょう。
屋根材や屋根の形状によって、必要な垂木の太さや長さは異なりますが、勾配のある屋根には必要な基礎です。必要に応じて長さをカットし、組み合わせて施工します。
ところで、垂木をすべて取り替えるとなると費用もかさみます。ですので、劣化具合などは写真を撮ってもらい、ご自身でも劣化具合を確認することをおすすめします。
工程3:コンパネ(野地板)の施工
コンパネとは、屋根の下地材のことであり、板状の四角い建材です。垂木の上に施工します。
屋根の形に合わせて施工します。9mm以上の厚みのものを使用しますが、太陽光パネルを載せる場合は12mm以上のものを使用すると決められています。通常は3尺×6尺の大きさのコンパネを使い、隙間なく並べます。
合板材を使うことが多いですが、耐久性のある無垢材を使うこともあります。無垢材は高価ですが、その分長持ちします。
コンパネと同じ役割の下地材として野地板と呼ばれるものがあります。一昔前の屋根では、垂木の上に現在よりももっと小さくて細長い板材が敷き詰められていました。これが野地板です。現在では、厚み9~12mm、大きさが90×180cm程度のコンパネが主流です。
工程4:ルーフィングの施工
ルーフィングとは、屋根における防水の役割を果たすシートのことで、コンパネの上に敷きます。
防水シートは、雨漏りを防ぐ上では最も重要な役割を担っています。雨水の侵入を防いでいるのは、屋根材やコンパネではなく、実はこのルーフィングです。もちろん屋根材にも防水機能はありますが、ルーフィングを敷かなければ雨水などを完全に防ぐことはできません。
耐用年数はおおよそ20年といわれ、葺き替えの際には必ず新しいものと交換します。
瓦屋根の場合
瓦屋根の場合、瓦をしっかり固定するために必要な工程があります。工事期間は1週間~10日程度が多く、他の屋根材と比較すると工期は長めです。
工程5:桟木の施工
瓦屋根の葺き替え工事では、ルーフィングの施工後に桟木の施工をします。桟木とは、瓦を固定するための細長い木材で、瓦の大きさに合わせて横向きに何本か施工します。そこへ瓦を引っ掛けて固定するのが一般的な工法です。これで地震などでも瓦がずれ落ちたりしないようにすることができます。瓦屋根の葺き替え工事では必要な工程です。
また、ルーフィング材と桟木の間に少し隙間をつくることで、雨水を排出するとともに、瓦からの熱を屋内に伝えない役割も担っています。
工程6:瓦葺き
瓦屋根の葺き替え工事では、桟木の施工の後に、いよいよ瓦の施工をします。瓦の裏側には桟木に引掛けるための突起があります。それをルーフィングの上に施工した桟木に1枚ずつ引っ掛け、さらに釘で固定していきます。
以前は、土を使って葺き替えをしていたため、簡単に瓦がずれたり落ちたりしていました。桟木に引っ掛ける工法により、瓦の安定感は飛躍的に増しました。また土よりも軽量な桟木を使うことで、建物に与える負荷が減り、地震対策にもなっています。
スレート屋根の場合
スレート屋根は瓦屋根より工程が少ないため、工期も短めです。屋根の状況や人手によっても工期は変わりますが、4日~1週間ほどで施工できます。
工程5:スレート材の施工
スレート屋根の葺き替え工事では、防水シートであるルーフィングの後にスレートを施工していきます。軒下から棟に向かって釘やビスで固定する方法で、一枚一枚順番に施工していきます。頂上である棟の部分の施工が終われば、スレート屋根の葺き替え工事は完了です。
ガルバリウム屋根の場合
ガルバリウム鋼板もスレート材と同様、屋根に直接打ちつけます。工期も同じくらいで、4日~1週間ほどと考えてよいでしょう。
工程5:ガルバリウム鋼板の施工
ガルバリウム鋼板の屋根葺き替え工事では、ルーフィングの後に屋根材を施工していきます。防水シートの上にステンレスの釘にて屋根材を固定していく方法です。
ガルバリウム屋根には、屋根材を横に並べる横葺きと縦に並べる縦葺きがあります。縦葺きは勾配に沿って自然と水が流れますので勾配が小さいデザインでも安心ですが、横葺きは水の流れが悪くなりますので、勾配が小さい屋根では雨漏りが起こる可能性もあり、注意が必要です。
ルーフィングの種類
防水シートのことを指す「ルーフィング」にもいくつか種類があります。現在、用いられているルーフィングにはどのようなものがあるか、それぞれの特徴を紹介しましょう。
アスファルトルーフィング
アスファルトルーフィングとは、板紙をアスファルトでコーティングしたルーフィングのことです。アスファルトルーフィングを「ルーフィング」と呼ぶ場合もあります。高い防水性・防湿性を持ち、勾配が小さい、あるいは勾配がなく平らな屋根にも適した建材です。一般住宅の屋根をはじめ、マンションやビルの屋上にも採用されています。
日本でアスファルトルーフィングが使われ始めたのは大正時代。広く普及したのは関東大震災後です。近年では改良が重ねられ、改質アスファルトルーフィングと呼ばれるものが登場しています。従来のものと比べ耐久性が高く、耐用年数は20年程度です。
アスファルトルーフィングは、貼り重ねることでより高い防水効果を得ることができます。これをアスファルト防水といい、熱工法、トーチ工法、接着工法、常温粘着工法などがあります。信頼性の高い防水層が必要な場所で用いられる工法です。
合成高分子系ルーフィング
合成高分子系ルーフィングとは、素材にゴムやビニル樹脂などを使った防水シートのことです。柔軟で下地にフィットしやすいのが特徴です。接着性が良く、古いルーフィングを撤去することなく重ねて施工することができます。繰り返しの伸縮にも耐え、耐久性にも優れています。工場でシート状に製造されるため、防水層にはバラつきがなく均一です。
また一層防水のため、工程が少なくて済みます。工事期間の短縮が可能です。
透湿ルーフィング
透湿ルーフィングとは、湿気を外に排出できるように設計された通気性の良い防水シートです。
空調などによって排出される湿気を含んだ空気は、天井にたまると結露を起こします。屋根裏にできた結露が原因で内部が腐食を起すと、屋根はもとより住宅そのものの寿命をも縮める可能性があります。
透湿ルーフィングは、住まいの湿気を排出できるよう、通気性を高めています。それでいて防水性には優れていますので、もちろん、本来の役割である防水機能に問題はありません。呼吸できる屋根、といったイメージです。
通気性が良いので湿気だけでなく、有害な化学物質なども外に排出します。また、軽量で施工性に優れています。コンパネや野地板の劣化を抑え、屋根の寿命を延ばせる優秀な下葺き材として注目されているルーフィングです。最近では屋根のほか、壁の下地として使われることも多くなりました。今後も研究が進められ、需要が増えると予想されます。
遮熱ルーフィング
遮熱ルーフィングとは、下地材にアルミなどを使って遮熱効果を高めたルーフィングのことです。紫外線や太陽熱を遮断し、屋内に熱が伝わらないようにすることで、夏場の暑さを軽減します。アスファルト・合成高分子・透湿、どのルーフィングにも遮熱性能をもたせたものがあり、これらすべてが遮熱ルーフィングと呼ばれるようになりました。
夏に屋根裏がとても暑くなるのは、屋根材が熱を吸収するからです。その熱が屋内にまで伝わり、屋根裏が特に高温になるという仕組みです。遮熱ルーフィングは、屋根の熱を屋内に伝える前に熱源をはね返すため、屋内の温度上昇を抑えることができます。省エネにもつながり、日差しが強い地域では特に効果的です。