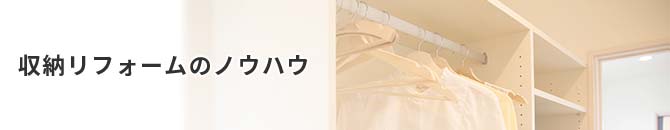
基礎知識
床下収納の設置に適した場所や種類を紹介!リフォームで作る場合の注意点も
公開日:2020年01月21日
土地や建築費の高さから、日本の家は狭くなりがちです。無駄なく空間を活かして、広々とした居住スペースを確保したいところです。
そんなときに考えるのが、床下収納でしょう。木材の防腐等の目的で、床下に大きな空間があることが多い木造住宅。床下収納を上手に設置して、居住スペースを広々と使いたいものです。
ここでは、床下収納をリフォームで作る場合の注意点をご紹介しています。検討されている場合は、ぜひ参考にしてください。
そもそも床下収納をリフォームで設置できるのか?
そもそも、床下収納をリフォームで後付できるのか?という疑問が出てくると思います。その答えは、市販の床下収納であれば40cm程度の深さがあれば設置可能です。それは、床下に潜んでいる一般的な隙間空間の深さです。扉廻りにちょっとした補強は必要になりますが、リフォームで床下収納を設置することは、特別な話ではありません。
床下収納をリフォームで設置できない4つのケース
ただし、リフォームで後から床下収納を設ける場合、どこでも好きな場所に設置できる訳ではありません。建物の現状を把握しながらの検討が必要となります。
1.床下空間が極端に狭い
高さ制限等で階高が低く、床下の高さを確保できていない場合、市販の床下収納は設置できないケースがあります。大工さんにお願いすれば、浅い床下収納も製作可能ですが、設置してメリットがあるかどうか、よく考えてから進めましょう。
2.設置したい部分に、基礎や梁などの構造物がある
基礎や梁など、構造部材は必ず避けて設置しましょう。木造の場合、梁なども容易にカット出来てしまうので、うっかりダメな位置を指定してしまうと、そのまま工事される可能性もあります。取り返しのつかないダメージを建物に与える可能性があります。
3.配管設備が密集している
キッチンや脱衣室廻りなど、配管が集中している場所に設置するときも、十分な検討が必要です。設置スペースがとれるかどうかの他、漏水等がおきた時に被害が無いか、配管等のメンテナンスに支障がないかも考慮して計画しましょう。
4.基礎の人通口・通風口を塞いでしまう
基礎の立ち上がり部分には、点検のため、人が通れるようになっている場所があります。そこを塞いでしまうと、後々のメンテナンスに支障が出てしまいます。また、床下の通風口近くに、空気の流れを妨げるように設置することも、建物の寿命を縮めることになるので注意してください。
床下収納の種類
床下収納には、目的や設置場所によって様々なタイプがあります。それぞれの特徴を考慮し、最も自分に合った使い方を検討してみましょう!
扉式
よく見られる、一般的な床下収納です。安価ですが収納量は限られます。キッチンに良く設置されているタイプです。
内部スライド式
扉式と外見は同じですが、収納部分が床下でスライド出来るようになっていて、収納量が増えます。収納面積に対して扉が小さいので、物の出し入れはやや不便です。
跳ね上げ扉タイプ
たたみ一畳分くらいの扉が開閉する、大きな収納。収納物を見渡すことが出来、使い勝手が良いです。広い空きスペースが必要なので、寝室や和室などに設置することが多いタイプです。
キャスター付きBOXなどを活かした床下収納
防湿処理や換気がきちんとされた家の床下は、夏は涼しく意外と悪くない環境です。床に扉を設けて、基礎上に市販のキャスター付き収納BOXを置いてみましょう。
収納物MAPを作っておけば、どこに何を仕舞ったか一目瞭然!BOXに紐を結んでおくことで、出し入れもスムーズ!収納量も多く初期コストも抑えられる、上級者向けの方法です。
床下収納を設置することに適した場所
収納する物によって適した設置場所は様々です。たとえ二階の床であっても、床下に空間があり、床を開閉させるスペースが確保できれば、どこでも床下収納化することは可能です。
ここでは、一般的に床下収納を設置すると便利な場所をあげてみます。
キッチン

床下収納を最も良く設置する場所。開口面積が狭い、扉式、スライド式を通路部分に設置することが多いです。頻繁に出し入れしない、ストック分の食材などを仕舞っておくと便利です。
寝室・リビング
一定の空きスペースがあるので、床跳ね上げ式の収納が設置可能。子供の思い出の品など、使わなくなったけど捨てられないものや、季節ごとの衣類、スキーやシュノーケルなどの装備品をしまっておくことが出来ます。
和室

跳ね上げ式の収納が設置されることが多いですが、固定家具を置くことが少ない和室は、全面を床下収納として使うことも可能です。畳を上げて、下地材を外せるようにしておけば、大容量の収納空間が現れます。畳や下地の上げやすさ、断熱材の施工方法、床鳴りの防止など設計上の配慮が必要となります。
床下収納を設置するメリット3つ
冒頭で述べたように、狭くなりがちな日本の住宅。床下収納の設置には、多くのメリットがあります。
未利用空間を活かせる
壁と屋根で囲われ、ある程度の環境性能が確保されているにも関わらず、床下空間は存在すら気にかけてもらうことの少ないデッドスペース。そこを活用できることは非常に有効です。
収納量が増える
収納タンスなどを置くと、だんだんと生活空間が狭くなって行きますが、デッドスペースを活用することで、住まいの快適性を損なわずに、収納量を増やすことが出来ます。
床下点検口としても使える
収納部分が取外しできるタイプを設置すれば、床下収納の開口は、床下点検口としても使うことが出来ます。将来的なメンテナンスなどにも使える位置に設置できると便利です。
床下収納を設置するデメリット4つ
人が歩く床に穴を空けて設置することになるので、デメリットも存在します。設置してから後悔しないよう、把握しておきましょう。
出し入れが不便
特性上、足元より下の位置に物を出し入れするため、窮屈で不安定な態勢で使用することになります。設置したけど使われないことも多いのは、このためだと思います。
段差ができる
開閉部分には、枠を設置しないと床材などの納まりが上手くいきません。ほんの少しの段差ですが、キャスター付きの家具を移動するときなど、凸凹が気になります。小さい子や、お年寄りは特に、ほんの小さな段差でも躓くことがあるので注意が必要です。
軋み音がすることがある
物の出し入れ口は、開け閉めできるようにするため、完全に固定することが出来ません。そのため、季節ごとの気温や湿度の変化、上を歩くことによる扉の変形や劣化により、床鳴りが発生することがあります。
断熱性能が落ちる(断熱収納以外の場合)
床下収納は、断熱性能が無いものが多いです。断熱材が施工されている床面においては、床下収納の所だけ、断熱性能が落ちることになります。全体で見れば看過できる程度の問題かと思いますが、収納内外で結露が発生する可能性もあるので注意が必要です。
床下収納に適さない収納物
床下収納は、位置や収納方法が特殊な分、収納に適さないものも多くあります。
普段良く使うものは避ける
最大のデメリットともいえる、使うときの窮屈で不安定な姿勢。普段良く使うものを入れると、面倒すぎて使わなくなることが多いです。
重い物はNG
重い物に関しても、腰への負担が大きいので、出来るだけ避けたほうが良いでしょう。食料品のストックくらいの重さ(最大3Kg程度)を限度としておくのが現実的だと思います。
湿度や温度管理が重要なもの
ひな人形や、五月人形、想定外に大きなものを頂いた場合、仕舞うところに困ります・・・・でも、そういったデリケートなものは、床下に収納することは避けましょう。床下収納は、基本的に密閉されており、温度や湿度は管理しづらい空間です。また、結露の発生などにより収納物にダメージを与える可能性があります。
床下収納に適した収納物
床下に仕舞うものとして適しているのは、普段使いしない、比較的軽く、湿気や温度の変化に強いものとなります。
食品のストック
キッチンに設置する場合は、ストック用の調味料や缶詰などが主流になると思います。湿気などに耐えうる、密閉された食品が適しています。
子供の工作等思い出の品(短期的には必要ないもの)
子供の工作や成績表など、思い出の品はどんどん増えて行き、収納が埋まって行きます。次に取り出すのは数十年後になるようなものは、床下収納にもってこいのアイテム。ビニール袋に密閉して、除湿剤と一緒に仕舞っておきましょう。
まとめ買いしたもの
量販店で大量に買ったものをストックしておく場所としても適しています。但し、トイレットペーパーなどのかさばるものを収納すると、直ぐに一杯になってしまいます。ごく軽いものは天袋収納などの高いところに収納し、床下収納と使い分けると良いでしょう。
腐らないもの
床下収納は、外からの確認が面倒なので、仕舞ったまま忘れ去られることが多い収納場所でもあります。どこに何をしまったか、扉を空けなくても分かるよう、メモを残しておきましょう。
忘れてしまった時のため、長らく収納しておいても腐らないものに限定して仕舞うと安心感があります。例えば、実家から大量に送られてきた根菜類は、一時的な保管場所としては有効ですが、そのまま忘れてしまうと大変なことになります。
床下収納を設置する際の注意点3つ
色々と床下収納について述べてきましたが、特に気にかけて欲しいのは以下の部分です。
日常生活の障害とならないように
開口部分には小さな段差が出来ます。お年寄りや小さいお子様がいらっしゃる時は、日常動線も考えて位置を決めましょう。床の軋みも発生しやすいので注意が必要です。
使いやすい収納になるように
窮屈な姿勢で利用することを前提に、仕舞うものの大きさや重さを検討して設置しましょう。仕舞ったまま忘れてしまわないよう、収納MAPを作成すると効率的です。
家の性能を損なわないように
構造体を傷めることなく、他の部分の点検の障害にならず、床下の通気などを妨げてしまわない位置に。図面をチェックして適切な場所に設置しましょう。
まとめ
床下収納は、未利用空間を有効に使う優れた手法ですが、設置の仕方によっては、お金を払って不必要なダメージを建物に与えた上、使わない大きな箱を作ってしまう可能性もあります。
充分に検討した上、リフォーム会社などの専門家のアドバイスを受けながら検討すればベストだと思います。