
床材
カーペット
公開日:2015年08月05日
カーペットとは部屋に敷き詰める大きな敷物のことで、絨毯(じゅうたん)ともいいます。断熱効果があり、ウールやナイロンなどの繊維素材でできている柔らかい床材です。色彩のバリエーションが豊富で、重要なインテリアの一部でもあります。
カーペットのメリット

メリットのひとつは、吸音性に優れていることです。
そのままでは足音や物音が階下に響いてしまうフローリングの床であっても、カーペットを敷くと足音はほとんどしません。カーペットが音を吸収するため、物を落とすなどしても音漏れを最小限にできます。
また、柔らかい素材でできているため足が疲れにくく、裸足で歩いても肌触りが良いです。繊維の摩擦で滑りにくい、万が一転んでも怪我をしにくい、そして高級感があるのもメリットです。
カーペットのデメリット
カーペットのデメリットとしては、まず掃除のしにくさです。カーペットは繊維でできているため、繊維の間にゴミが入り込みやすく、取りにくいというデメリットがあり、清潔を保つのは大変です。シミなどが染み込んでしまうと、なかなか取れません。
ホコリやフケ、アカなども完全に取り除くのが難しいため、繊維の奥にダニが発生しやすい環境になります。また、夏は見た目も実際の肌触りも暑苦しく感じてしまうことや、キャスター付きの家具が移動させにくいこともデメリットと言えるでしょう。
カーペットの素材
天然繊維(ウール)
天然繊維のウールには、天然ならではの肌触りの良さと高級感があり、長期間弾力性を保てるのが魅力です。表面は皮膜で覆われており、汚れにくく静電気が起きにくいのが特徴です。保温性、吸放湿性にも優れ、快適な室内空間を演出します。但し天然繊維であるがゆえに虫やカビが発生しやすい、という難点があるため、防虫加工がされたものを選ぶのが望ましいでしょう。
合成繊維(ポリエステル・ナイロン・アクリル)
合成繊維にはポリエステルやナイロン、アクリルなどがあります。全般に虫がつきにくく、丈夫で価格が手頃であるというのが魅力ですが、防音性、保温性、肌触り、弾力性は天然繊維より劣ります。しかし、ナイロン、ポリエステルは摩耗に強い特徴があり、人通りの多い場所にもよく使われます。ウールに比べると水を吸収しにくいため、液体の汚れをさっと拭き取れるメリットがあります。アクリルは柔らかく、ウールに似た風合いを持っていますが、燃えやすいので耐燃加工されたものを選ぶのが望ましいでしょう。
毛足の形状
| カットタイプ | パイル糸を表面でカットした毛足の形状です。毛足の長さは5~10mmが一般的ですが、カットの方法によっては30mm以上、中には100mmというものもあります。 色の変化や深みを醸し出すことが特徴で、歩行量の少ない部屋に向いています。 |
|---|---|
| ループタイプ | パイル糸をカットせずにつなげたまま織り込んでいく形状です。各ループの長さが揃っているものや、大きさ、長さが不規則なものがあります。カット面がないため弾力性があり、耐久性にも優れています。適度な硬さと滑らかさがあり、歩きやすいのも特徴です。また、ホコリが奥に入り込みにくいので掃除がしやすく、子供部屋やリビングに適しています。 |
| カット&ループタイプ | カットタイプとループタイプを組み合わせてそれぞれの欠点を補い、絶妙な毛足の形状を表現したタイプです。装飾性が高く、色や柄、素材や織り方などさまざまな組み合わせで作ることができます。 |
製造方法
カーペットの主な製造方法は織物と刺しゅうで、最も歴史が古いのは織物の手織です。大変高価ですが、一生ものと言われるほどのカーペットです。ほかには縫い付け、接着、フェルトなどがあります。
| 織物 | 織物とは、縦糸と横糸を芯で織り込んでいる製造方法で、耐久性に優れています。接着剤等を使用していないので、健康被害の心配もありません。手織に比べると手頃な機械織りには長さを自由に変えられるウィルトン織、2枚同時に作れるダブルフェース織、細い糸を使うジャガード織が代表的な織り方です。 |
|---|---|
| 刺繍 | 刺しゅうは、糸を植え付けて、裏側にもう1枚布を接着剤で貼り合わせる方法です。刺しゅうにも手作業と機械があり、機械刺しゅうの代表的なものがタフテッドです。多数のミシン針を使うため大量生産が可能であり、高価なカーペットを大衆向けに広げた画期的な方法です。手作業は、機械に比べると高いですが、手織りよりは安いのが特徴です。 |
カーペットの種類
カーペットの中でも製造方法や毛足の形状によってさまざまな種類が存在します。その中でも代表的なカーペットをいくつかご紹介します。
ウィルトンカーペット
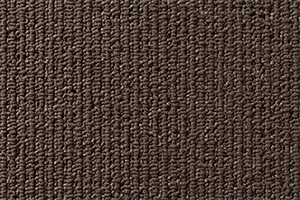
2色から5色のパイル糸を使った機械織りの代表的なカーペットです。18世紀中ごろにイギリスのウィルトン地方で始まったことからこう呼ばれています。密度が細かく、耐久性があります。19世紀にジャガードを使用したものが作られ始め、現在では区別されていますが、織り方は同じです。パイル糸の長さに変化を持たせることで、多種多様な織方法が可能です。
タフテッドカーペット
パイル糸を織り込むのではなく、基布にパイル糸を植え付けて、裏面に接着剤をコーティングし、化粧裏地を貼り付ける方法でつくられたカーペットです。刺しゅうという製造方法の中で代表的な種類です。価格が手頃でカーペットの普及に貢献したため、最も多く出回っています。
アキスミンスターカーペット
19世紀後半からつくられている機械織りカーペットです。ウィルトンと製法は同じですが、ウィルトンが2~5色のパイル糸を使うのに対し、8~12色の多色使いが可能です。イギリスのアキスミンスターでつくられ始めたことから名付けられました。多彩な色柄はとても豪華で、ホテルの宴会場などによく使われています。
タイルカーペット
45cm角、50cm角といった小さなタイル状のカーペットを敷き詰めるタイプです。好きな場所に必要な分だけ敷き詰められる施工のしやすさから、もともとはオフィスや会議室使用が主流でしたが、最近は住宅用としても人気があります。
カーペットの手入れ方法
日頃の手入れの仕方
カーペットの日頃のお手入れは、週に1~2回の掃除機がけです。
パイルの奥に入り込んだホコリやゴミを取り除くため、パイルとは逆方向に、パイルを起こすように丁寧にかけるのがコツです。
パイルの方向に押さえつけると、かえってゴミが中に入り込んでしまいます。
また日頃からダニの発生を抑えるために換気に気を付けるようにしましょう。パイルが飛び出している部分ははさみで切り揃えると良いです。
月1回の手入れの仕方
月に1回程度は、染みついた汚れや臭いをとるため拭き掃除をします。中性洗剤を薄めたお湯で雑巾を固く絞り、最初はパイルの方向に、そのあと逆の方向に拭きます。色落ちなどを確認するため、はじめは部分的に行い、問題がなければ全体を拭くようにします。
その後、洗剤が残らないように水拭き、乾拭きをします。乾拭きの後はパイルが立つようにブラッシングし、充分に乾かします。行う際は、換気しながら行いましょう。
年に1回の手入れの仕方
年に1度は裏返して半日ほど陰干しします。中に入り込んでいるゴミやホコリを落とすため、裏から棒などで叩くと効果的です。陰干しをするのは変色を防ぐためです。干している間にカーペットを敷いている場所を掃除し、風を通しておきましょう。
カーペットの大敵は湿気です。湿気がたまるとダニが発生しやすくなりますので、日頃から風通しを良くして湿気をためないようにすることが大切です。